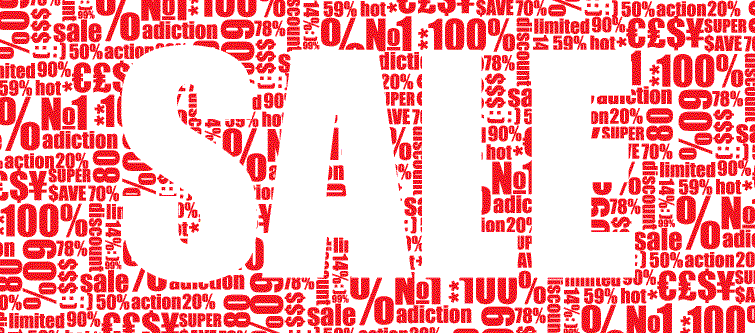いよいよです!
本日の深夜、ついにnVidiaの新GPU GeForce GTX 1o80が降臨します!秋葉原のドスパラやパソコン工房、ツクモなどのショップは深夜販売も計画しています。
当サイトをいつも読んでいただいているあなたは、たぶんスタンバイ済みで、今日はそこらじゅうから上がるベンチ報告で眠れないことでしょう!(もしくはアキバで行列中?)
ですが、「え?なにか始まるの?GTX 1080ってなに?」という方も多いはず。今日はGTX 900シリーズと新10シリーズのスペックを比較しながら、なぜこれほどの祭りになっているのか解説していきたいと思います。
新世代
まず押さえたいのはGTX 10シリーズ(1000シリーズ)はまったくの新世代シリーズという点です。
コアアーキテクチャが「Pascal(パスカル)」となり、これまでで最高の微細化、低電力化、高クロック化を果たしています。
GTX 900シリーズは、コアアーキテクチャが「Maxwell(マックスウェル)」と呼ばれる技術でした。さらに前のGTX 700シリーズはKepler(ケプラー)という名前でした。(デスクトップ用は800番台は欠番)
Kepler → Maxwell → Pascalのそれぞれの進化で、およそ2倍ずつ処理能力はアップしてきています。Maxwellの描画能力も相当なものでしたが、Pascal世代ではそこからさらに倍近い能力を秘めているということです。
スペック比較
スペックを比較しましょう。
| GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForceGTX TITAN X | GeForce GTX 980Ti | GeForce GTX 980 | GeForce GTX 970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャー | GP104 (Pascal) |
GP104 (Pascal) |
GM200 (Maxwell) |
GM200 (Maxwell) |
GM204 (Maxwell) |
GM204 (Maxwell) |
| 製造プロセス | 16n FinFET | 16n FinFET | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
| ストリーミングプロセッサ | 2560基 | 1920基 | 3072基 | 2816基 | 2048基 | 1664基 |
| コアクロック | 1607MHz | 1506MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1126MHz | 1050MHz |
| ブーストクロック | 1733MHz | 1683MHz | 1075MHz | 1075MHz | 1216MHz | 1178MHz |
| テクスチャーユニット数 | 160基 | 120基? | 192基 | 176基 | 128基 | 104基 |
| ROP数 | 64基 | 64基? | 96基 | 96基 | 64基 | 56基 |
| メモリー転送レート | 10GBps | 8GBps | 7GBps | 7GBps | 7GBps | 7GBps |
| メモリータイプ | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| メモリーバス幅 | 256bit | 256bit | 384bit | 384bit | 256bit | 256bit |
| メモリー搭戴量 | 8GB | 8GB | 12GB | 6GB | 4GB | 3.5GB+0.5GB |
| TDP | 180W | 150W | 250W | 250W | 165W | 145W |
| 外部電源 | 8ピン | 8ピン | 8ピン+6ピン | 8ピン+6ピン | 6ピン×2 | 6ピン×2 |
今回先頭を切って発売されるのはGTX 1080。少し遅れてGTX 1070の予定です。今回は仕様が確定しているGTX 1080に解説を絞ります。
注目すべきポイントを赤文字にしました。
まずはいまだかつてないコアクロックです。今までは高くても1000MHz(1GHz)、サードパーティの大型ファンを搭載したタイプで1200MHz程度でしたが、GTX 1080は最初から1.6倍もの1607Mhzになっています。さらにブーストクロックは1733Mhzに達しています。
これは省電力化で熱が抑えられたために実現できたものでしょう。Maxwellで1700Mhzを実現しようとすると水冷でも危険なほどで、それこそ窒素冷却が必要でしょう。
また微細化によりCUDAコア数も大幅にアップ。最初からGTX 980Tiと同じ規模の2560基となっています。このコア数を1600MHzでブン回すので、その底力はものすごいでしょう。いずれ出てくるであろうGTX 1080Tiや新TITANは、きっと目もくらむような描画速度を叩き出すはずです。
GPUだけが早くなっても、データの供給が追いつかなければ意味がありません。そこで初採用のGDDR5Xメモリです。
いままでのGDDR5から2倍の転送レートとなる新メモリです。ただ、まだ製造が始まったばかりで、今回のリファレンスモデルでは10GBpsに抑えられています。将来は14GBpsまで速度がアップされるとなっています。
ただ、メモリに関してはさらに広いバンド幅を持つHBMがあり、nVidiaも開発中なのでTITANなどはHBMを採用するかもしれませんね。
その他にもVR(バーチャルリアリティ)用に、2つの角度からの映像を同時に生成する機能(Single Pass Stereo)や、処理スケジュールの最適化、DirectX 12への最適化などが盛り込まれています。
価格が安い!
ということでスペック表を見てきましたが、まだイマイチわからん!という人のために価格で言ってしまいましょう!
実質的なコストで言えば「GTX 980~980Tiほどの価格でTITAN Xの能力が買える」と言えます。各社のベンチマークではTITAN Xを超え、GTX 980 SLIに迫るというから恐ろしい。
いままででは12万円コースだった性能が、10万円以下で買えるのです!(最初は高いかもしれないけどね・・・数ヶ月で落ち着くはず)
今回祭りになっているのはここが一番の注目点でしょうね。
WTS的まとめ
ということで本日の発売、楽しみですね~~!ウェブでの注文、予約も今夜から始まりそうですよ!
ウェブでの注文はこちらから!
![WorkToolSmith [ワークツールスミス]](https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2014/11/d30716bfc62ca82b12c303b90f356916.png)