組み立て
組み立てはごく一般的なmini-ITXとほとんど変わりません。ただ、細かいネジ留めの方法や、どのネジを使うのかなどがマニュアルに一切書いてない!
自作に慣れた人ならいいでしょうが、はじめてでは間違ったネジを使ってしまいそう。またドライバーはかなり細いものが必要でした。
まずM.2 SSDを設置します。
なぜかというと、CPUのプレートを付けるとその下になって、ヒートシンクが取り外せなくなるからです。

CPUファンプレートを付けるとM.2のヒートシンクが外せない
ヒートシンクを取り外し、内側の熱伝導体のシールを忘れずはがします。

ヒートシンク付きを外す
M.2は2スロットありますが、熱伝導体は大きな1枚でした。

熱伝導体は大きな1枚
SSDを差しこみ、ネジ留めすればOK。ファンの端子も忘れずに挿しましょう。
次にCPUファンです。付属の2本のステーを取り付け、その上にファンを取り付けます。
CPUはセットアップ済みなので、緊張しながらソケットに入れたりグリスを塗ったりなど、初心者がつまづきやすい作業がないのがうれしい。

CPU用のファンステーの取り付け
ネジはこの6個入りのもの。

CPUプレート用のネジ
このプレートはM.2側、PCIeスロット側のどちらかにオフセットできます。用途に応じて選べます。
PCIeスロットを使う予定がなければ、PCIeオフセットさせておくとM.2 SSDの交換が簡単になります。
CPUファンを設置。使うのは一番長い4本のネジです。プレートは空中に突き出しているので、裏から押さえながら締めないと曲がってしまいそう。気をつけたい。
しかもネジはネジ止め剤でけっこう固い。穴をナメないようにも気をつけましょう。
CPUファンコネクタはATX端子の後ろ側になります。忘れずつなぎましょう。
次にバックプレートです。
そのまま取り付けようとしたら、無線アンテナのナットで奥まで入りません。このアンテナ部分のナットを外して、プレートを入れてから、また締めないといけません。
もちろんマニュアルには書いてない。(笑)
- 根元にナットが止まっている
- ナットはラジオペン字などでゆるめる
- 取り外したところ
DP端子付近も2カ所のネジ留めが必要です。

DPとHDMI付近にもネジがある
使うのはこの2個入りの小さなネジ。ただしネジ穴がかなり小さいです。精密ドライバー(たぶん#0000とか)用だと思われます。筆者はその大きさを持っておらず、急きょ極細のマイナスドライバーで締めました。せめて#1や#0ぐらいの一般的なネジにしてほしい。


ピッタリのドライバーがなかったので、極細のマイナスドライバーでかろうじて締めた
起動
起動すると無事にBIOS画面が出ました。購入時点のバージョンは1.02。
設定は一般的なPCのような大まかなもので、オーバークロック項目などはありません。


設定可能な項目は一般的なPCと変わらない
ベンチマーク
ではベンチマークを取ってみましょう!
デスクトップ用 65WのRyzen 7 5700Gと比較してみます。
| Ryzen 7 7745HX(レビュー品) | 8コア/16スレッド ZEN4 dTDP 55W |
| Ryzen 7 5700G | 8コア/16スレッド ZEN3 dTDP 65W |
PassMark(CPUテスト)

| Ryzen 7 7745HX(レビュー品) | 34640 |
| Ryzen 7 5700G | 23233 |
Ryzen 7 5700Gから10000ポイントの大幅アップです!おどろきのスコア。
近いスコアのCPUを見ると、
- モバイル用Intel Core i9-12950HX(32,964)
- デスクトップ用 AMD Ryzen 7 7700(34,801)
- デスクトップ用 Intel Core i7-12700K(34,713)
などです。どれほどの実力か、うかがい知れます。
CINEBENCH R15(CPU)

| Ryzen 7 7745HX(レビュー品) | 3112 |
| Ryzen 7 5700G | 2112 |
CINEBENCH R20(CPU)

| Ryzen 7 7745HX(レビュー品) | 7455 |
| Ryzen 7 5700G | 4963 |
すべてのテストで30%もしくはそれ以上のスコアをたたき出しています!
デスクトップ用のRyzen 7 5700Gを完全に抜き去っており、競り合う場面すらありません。圧勝といえます。
最新のIntel 14シリーズや、Ryzen 9には及びませんが、それでも一時期のハイエンドを超えているのはすごすぎる。
電力を制限しないモバイルCPUのポテンシャルはあなどれません!
消費電力
消費電力を見てみます。比較対象はRyzen 7 5700Gです。最低電力、最高電力を比較しました。(HWiNFOによるログ取り)
Ryzen 7 5700Gも比較的省電力なタイプですが、アイドル時は18Wが最低値で、平均は20Wほどです。
Ryzen 7 7745HXはさすがにモバイル用CPUだけあって、アイドル時は見事に電圧が下がり、消費電力はわずか8W。1コア1Wぐらいしか消費していない計算です。豆電球か。平均は10W付近です。
高負荷時では、Ryzen 7 5700Gは85Wほどまで上がります。これまたデスクトップ用としては標準的。
逆にRyzen 7 7745HXは予想外に消費電力が上がり、なんと100W台に突入します。ノートPCではここまで上がることはまれだと思いますが、電力が豊富なデスクトップでは、フルパワーで一気に処理を終わらせようしている感じです。
モバイル用CPUだからどんな条件でも低消費電力だとは言えないようですね。
普段は低負荷の作業が多く、たまに高速処理が入るなら良いのですが、常に高負荷な状態では、予想外の消費電力となるかもしれません。
もちろん100Wなりの熱を発生しますので、安めのケースファン(be quiet! 12cmファン)ではバラック状態でも93℃まで上がってしまいました。
強力な風圧のXPG Vento Pro 120 PWMなら最高でも86.2℃で抑えきりました。ベンチマーク後もすみやかに温度が下がります。12cmファンはいろいろ選べますが、やはりファンの性能には気を付けたいところです。
それでも、少し前のCore i9に迫る性能を空冷で十分に抑えきることができるのは、Ryzen 7 7745HXならでは。このバランス感覚にピンと来る人は「買い」だと思います。
WTS的まとめ
以前はコアも機能も削って作られていたモバイルCPU。ですがRyzen 7 7745HXは、デスクトップ用Ryzenを低消費電力にアレンジしただけ、という感触です。
豊富な食事(電力)を与えれば、まるで食事制限をしていたボクサーが生き返ったかのように、非常に高いパフォーマンス発揮します!(笑)
小型PCでも熱をそれほど気にせず組み込め、しかも少し前のハイエンドに追いつくほどのスコアを記録する、非常に楽しいマザーボードです!おすすめします。
![WorkToolSmith [ワークツールスミス]](https://worktoolsmith.com/wp/wp-content/uploads/2014/11/d30716bfc62ca82b12c303b90f356916.png)







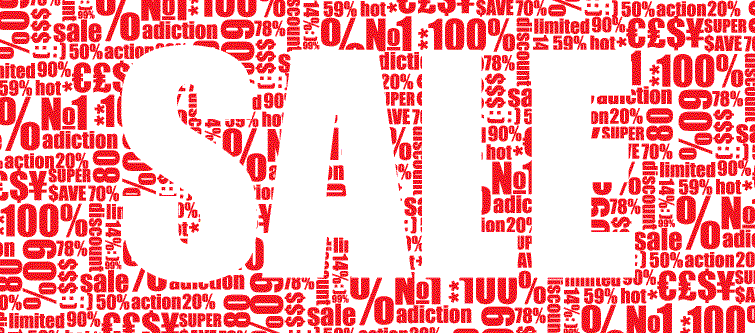

コメント